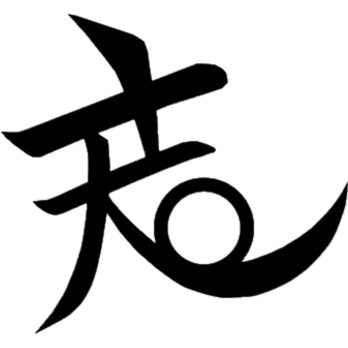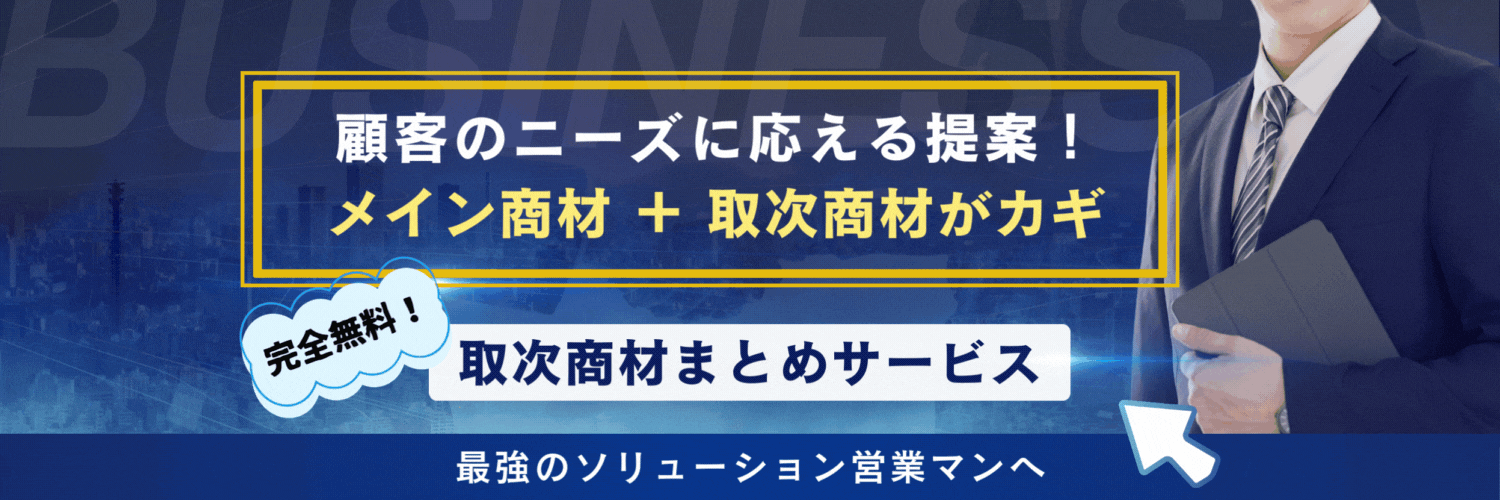はじめに
「もっと売れ」と言われながら、「売り込みっぽくするな」とも言われる。
この矛盾に悩んでいる営業マンは少なくありません。
数字が求められる営業の現場では、「売る力」が強い人が評価されがちですが、いま、確実にその常識が変わり始めています。
むしろ、「売らない営業」が顧客に選ばれる時代が来ているのです。
今回は、「なぜ売らない営業が信頼され、結果的に選ばれるのか?」その理由と実践ポイントを解説します。
「売らない営業」とは?誤解されやすいその本質
「売らない営業」と聞いて、こんな印象を持つ人もいるかもしれません。
- 押しが弱い
- セールスしないから売れない
- お客様任せで主体性がない
しかし、実際の「売らない営業」とは、顧客に無理をさせず、自然と『買いたくなる』状態をつくる営業のこと。
言い換えれば、「売り込まなくても売れる」状態をつくることに長けた営業スタイルです。
その背景には、顧客の購買行動の変化があります。
なぜ「売らない営業」が増えているのか?
- 顧客が情報を自分で集められるようになった
- 強引なセールスが敬遠される時代になった
- 顧客が「相談できるパートナー」を求めるようになった
今や、営業に求められるのは「物を売る能力」ではなく、「価値を一緒に見つける力」なのです。
顧客は、売ろうとする営業に飽き飽きしています。
時代が変わっていくことで、顧客が求める営業像も変化しています。
売らない営業が選ばれる3つの理由
では、なぜ「売らない営業」が顧客に選ばれ、信頼を得られるのでしょうか?
その理由を3つに分けて解説します。
1. 「買いたいタイミング」を尊重するから信頼される
売りたい営業は「今すぐ買ってほしい」と考えます。しかし、顧客のタイミングと一致しないと、それは押しつけになってしまいます。
売らない営業は、顧客の意思決定のペースを尊重します。
無理に急かさず、判断材料を丁寧に提供し、最終的な判断は相手に委ねる。
この姿勢が「信頼できる」「安心して話せる」という印象を生み、結果的に「この人から買おう」と思ってもらえるのです。
顧客は「今すぐ買ってほしい」という営業の気持ちを理解しています。
それでも顧客の気持ちを優先してくれる営業の姿勢に「信頼できる」「この人なら安心してお任せできる」となるわけです。
2. 顧客の「本当の課題」に寄り添うから響く
売ろうとすると、自社の商品やサービスの良さをアピールしがちです。
しかし、顧客が本当に知りたいのは「自分の問題を解決してくれるのかどうか」。
売らない営業は、商品ではなく顧客の課題にフォーカスします。
たとえば、次のような質問を重ねます。
- 「いま、どんなことに悩んでいますか?」
- 「理想はどんな状態ですか?」
- 「それが解決できたら、どんな良いことがありますか?」
こうした問いを通じて、顧客の本音を引き出し、それに対して必要であれば自社の提案を差し出す。
その順序が、顧客に「この人は売りたいんじゃなく、助けたいんだ」と感じさせるのです。
「自分の役に立とうとしてくれる」という姿勢が、顧客の心を掴み信頼関係を構築する鍵となるのです。
3. 長期的な関係を見据えているから選ばれる
売ることだけを目的にする営業は、契約後の関係性が希薄になりがちです。
一方、売らない営業は、売る前から売った後までを見据えた関わり方をします。
たとえば、
- 契約に至らなくても、業界の有益な情報を共有したり
- 他社の事例を紹介したり
- 将来的な展望について意見を交換したり
このように「売らなくても役に立つ」存在になることで、顧客の中で「信頼できる相談相手」としてポジションを築きます。
そして、その信頼があるからこそ、いざという時に「やっぱりあなたにお願いしたい」と選ばれるのです。
顧客から信頼してもらうことは、数をこなし続ける営業ではなく、積み上げる営業になっていきます。
つまり自分から営業をしなくても、顧客から商品やサービスの相談がくるようになるわけです。
実際に売らない営業で成果を上げた事例
ある営業マンは、新規顧客への初回訪問時に、商品の説明を一切しませんでした。
代わりに、次のような会話を重ねました。
- 「そもそも、御社ではどんな方向性を目指しているのですか?」
- 「業界の変化の中で、不安な点などありますか?」
- 「現状の課題は、どんなところに感じていますか?」
1時間ほどのヒアリングで、その会社が抱える構造的な問題や、潜在的な課題が明らかになりました。
その後、3週間ほど情報交換を重ねた上で、
「もしお役に立てるとしたら、こういう選択肢があります」と初めて提案。
結果、その提案は即決で受け入れられ、さらには他部門の紹介も得られることになったのです。
顧客の言葉にはこうありました。
「最初から売り込まれたら、きっと断っていた。でも、話を聞いてくれて、本当にうちのことを考えてくれたのが伝わったから、お願いしようと思った。」
今日から始められる「売らない営業」の実践ポイント
最後に、売らない営業スタイルを日々の営業活動に取り入れるためのポイントをまとめます。
✅ 商品の話は後回しにする
まずは相手の課題や背景を深く理解することに集中。ヒアリングに8割の時間を使ってもOKです。
すぐに商品の話をするのは、「売りたいんだな」と顧客に思わせてしまいます。
その結果、そのあとのヒアリングでも本音を話してもらいにくくなるためNGです。
✅ 「提案」は、選択肢の一つとして差し出す
「これを導入すべきです」ではなく、「こういう方法もありますが、いかがですか?」というスタンスが大切です。
顧客に選択する自由を与えつつ、なぜ自社の商品をお勧めするかを丁寧に説明しましょう。
この「なぜ自社の商品をお勧めするのか」が、誰にでも通る話ではなく、「提案している顧客にとって」であることが重要です。
✅ 「売らなくても価値がある」存在になる
情報提供、相談対応、紹介、共感。目の前の商談に関係しなくても、相手にとって価値ある行動を積み重ねましょう。
その積み重ねが、「何かあったときはこの営業さんに」や「知り合いが困っているから紹介しよう」と思わせる信頼関係を構築してくれるのです。
おわりに
売らない営業は、売れない営業ではありません。
むしろ、顧客から信頼され、「この人から買いたい」と自然に思ってもらえる営業スタイルです。
商品ではなく、人で選ばれる。
そのためには、「売ること」よりも「聴くこと」「理解すること」「寄り添うこと」に力を注ぐこと。
今すぐ売るのではなく、選ばれる営業になるための視点を持つことが、これからの時代の営業に求められているのです。