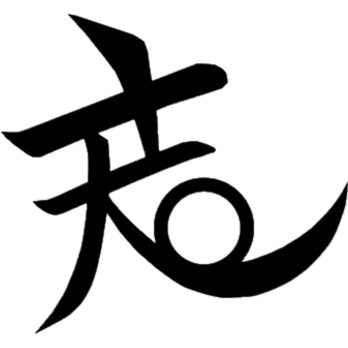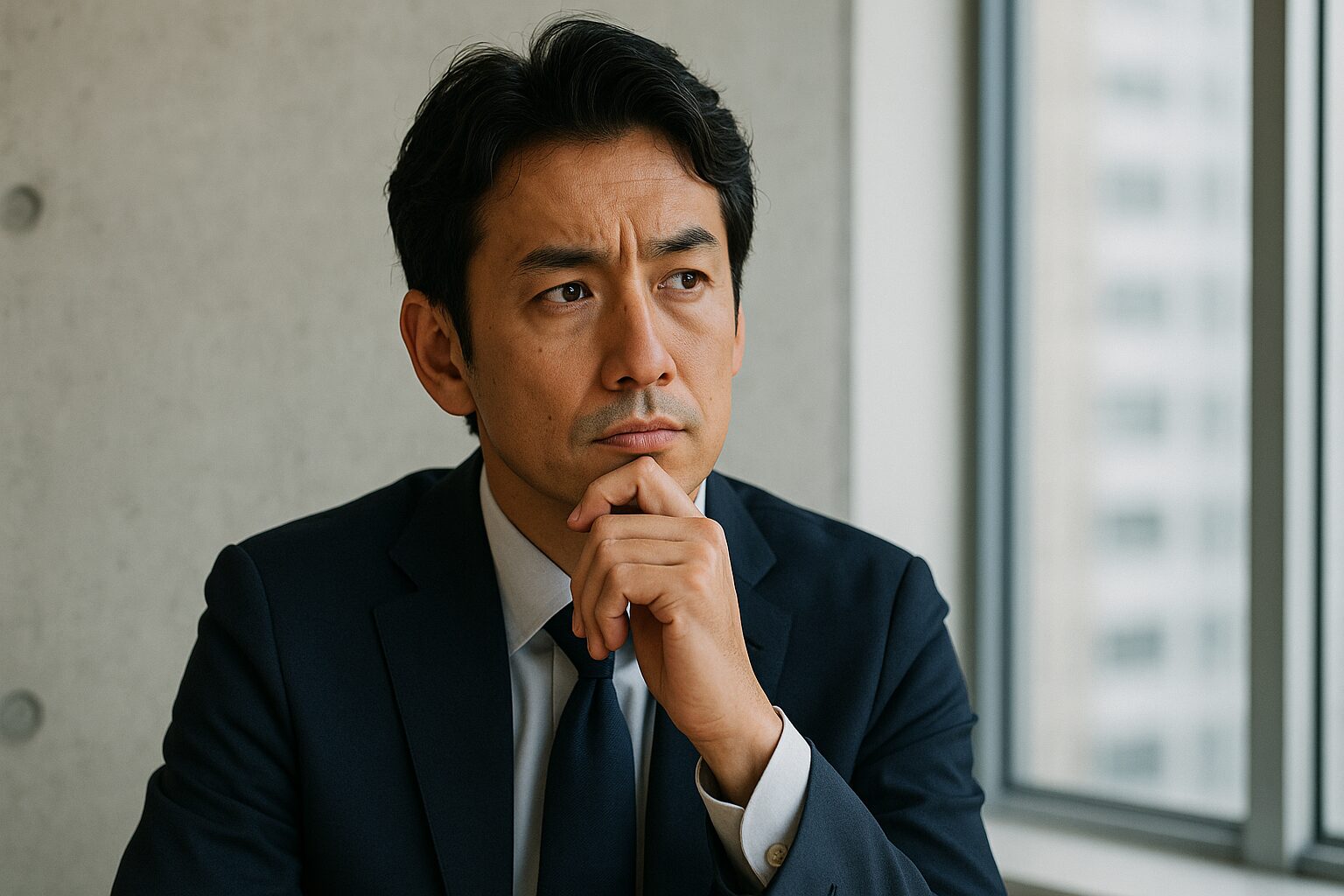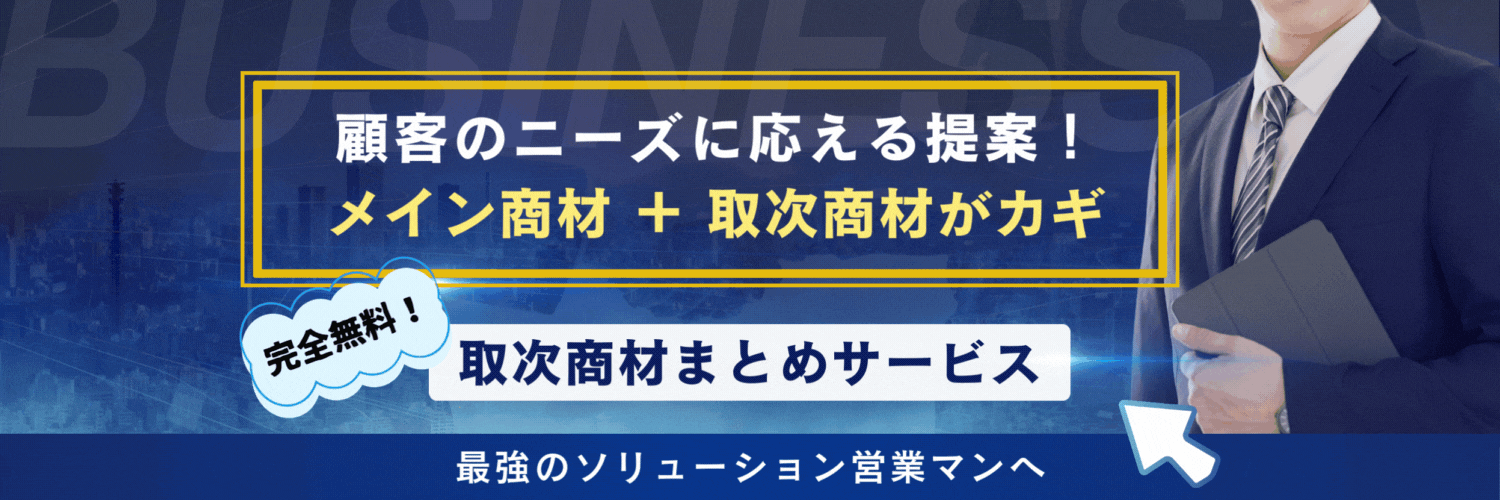お客様となぜか話が食い違う。
そんなことはありませんか?
通じ合えない原因は「思い込み」にあります。
「お客様のニーズを正しくつかみたい」
「ヒアリングしたはずなのに、なぜかすれ違ってしまう」
営業においてよくあるこのギャップ、実はある思考のクセが原因になっています。
それが、「主観」と「事実」の混同です。
人は無意識に、見聞きしたことを自分の価値観や感情で解釈し、話し、行動します。
しかしそれが、顧客との認識ズレを生み、「ちゃんと伝わっていない」「話が噛み合わない」結果を招いてしまうのです。
この記事では、営業活動においてなぜ「主観」と「事実」を分けて考える必要があるのか、具体的な例を交えて解説していきます。
なぜ主観と事実の区別が重要なのか?
営業現場でありがちなこんな会話を見てみましょう。
営業A:「先方、かなり怒ってたみたいです」
上司:「それ、どんな様子だったの?」
営業A:「口数が少なくて、目も合わせてくれなかったので……」
このやり取り、実は事実と主観が混ざっています。
- 事実:口数が少なかった、目を合わせなかった
- 主観:「怒っていた」と感じたこと
口数が少ない=怒っている、とは限りません。
体調が悪いかもしれないし、考え事をしていたのかもしれません。
しかし人は、目の前の情報を瞬時に解釈し、主観的な結論を出してしまうものなのです。
この「思い込み」が顧客との関係を難しくしている場面は、営業の現場に数多くあります。
よくある主観と事実の混同パターン
営業で顧客のニーズを正しく理解しようとするほど、主観と事実の区別は重要になります。ここでは実際によくある混同例を紹介します。
● パターン①:「興味なさそう」→ 実は集中して聞いていた
たとえば、プレゼン中に無表情で腕組みをしていたお客様を見て、「この人、興味なさそうだな」と感じたとします。
しかし終わった後、「すごく面白かった、検討します」と言われて驚いた、なんて経験はないでしょうか?
- 事実:無表情、腕組み
- 主観:興味がない
本当は集中して聞いていただけなのに、こちらが勝手に「響いてない」と判断してしまっていた。これは典型的な主観のバイアスです。
● パターン②:「価格がネックですね」→ 実は提案内容に納得できなかっただけ
顧客が「ちょっと高いですね。○○社のほうが安かった」と言った時、それを文字通り「価格が問題なんだ」と受け取って、値引きの話ばかりを持っていく営業は少なくありません。
しかし実際には、金額ではなくその価値をどう説明するかが問題だったケースもあります。
- 事実:価格が高いと言った
- 主観:価格がネックだと決めつけた
これは提案した内容に対して顧客が「価格が高い」と表現しただけの場合もあります。
値段ではなく、その提案内容が他社と比べてコスパが悪いと判断しているのです。
少し難易度が高い話ですが、ここでも発言の裏にある本音を探らず、表面だけを見てしまうことでニーズを取り違えてしまっています。
このような場合は、他社との違いを改めてご説明しつつ、反応を見てから値引きの話を提案するか判断しましょう。
営業で主観と事実を切り分けるためのステップ
では、実際の営業現場で主観と事実をどう切り分け、ニーズ理解に活かしていけばいいのでしょうか?
以下の3つのステップを意識するだけで、見える世界は大きく変わります。
① 「事実」を丁寧に観察する
まずは、自分が見聞きしたことを「事実」だけで捉える習慣をつけましょう。
「○○と言った」「○○という表情をしていた」「○○という資料を提示してきた」など、感情を交えずに、起きたことを冷静に整理することです。
ポイント!
「〜な気がする」
「〜っぽい」は主観。
証拠や根拠があるかを常に確認する。
② 主観が混じったと気づいたら「確認する」
自分の中で「きっとこうだろう」と思ったら、そのままにせず相手に確認を取りましょう。
たとえば、「今回の価格、少し高く感じられましたか?」と聞いてみることで、本当の理由や背景を聞き出せることがあります。
ポイント!
主観を仮説にして、必ず質問で確かめる。
③ 相手の「事実」と「主観」にも気づく
営業は自分自身だけでなく、顧客側の主観バイアスにも配慮する必要があります。
相手が「このサービスはうちには合わないと思う」と言ったときも、その根拠や背景を探ることで、「合わない」という主観が、誤解や過去の経験から来ているだけだったと分かることも。
ポイント!
相手の言葉の理由を深掘ることで、本当のニーズにたどり着ける。
主観を分けられる人は、信頼される
主観と事実を分けて考えられる営業は、顧客とのやり取りの中で「誤解」や「すれ違い」を減らせます。
だからこそ、「この人はきちんと話を聞いてくれる」「ちゃんと理解しようとしてくれる」と感じてもらえるのです。
逆に、自分の主観で決めつけて話してしまう営業は、知らず知らずのうちに信頼を失い、ニーズを外した提案をしてしまうリスクが高くなります。
主観と事実は常に意識しておくことが重要です
なぜなら人は、つい事実と主観を合わせて考えて、勝手に「相手はこう思っている」「こう考えているから、こう行動している」と決めつけてしまうからです。
このパターンでの事実は、「こう行動した」のみです。
相手がどう考えてその行動をしたのかは、相手に聞かないとわかりません。
この決めつけによるすれ違いは、営業の現場だけではなく日常で起きています。
あなたの周りの人との関係性においても非常に重要になるので、意識して考えましょう。
実践:主観と事実を分ける口グセを持とう
日常の中で主観と事実を意識するために、次のような口グセを使ってみるのもおすすめです。
- 「それは、○○さんが実際におっしゃったんですか?」
- 「私はそう感じたんですが、実際はどうなんでしょう?」
- 「今のは私の解釈かもしれませんが…」
このように主観と事実を明確に分ける会話ができると、主観に振り回されたすれ違いが起きにくくなり、事実に基づいた整理をすることができます。
また、このトークは部下に対して的確なアドバイスを行うのにも大変有効です。
まとめ:主観と事実を切り分ける営業が、ニーズを見抜ける
営業において顧客のニーズを深く理解するには、「相手の言葉をどう受け取るか」が鍵です。
そこに主観が入りすぎると、すれ違いが生まれます。
事実を丁寧に捉え、主観は確認し、相手の真意に迫る
その積み重ねが、相談され、信頼される営業をつくります。
主観と事実を意識して切り分けられるようになったとき、営業の精度は格段に上がります。
ぜひ、明日からの一言一言を見直すことから始めてみてください。