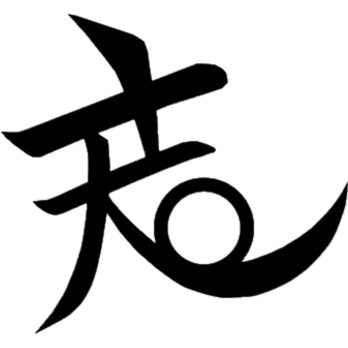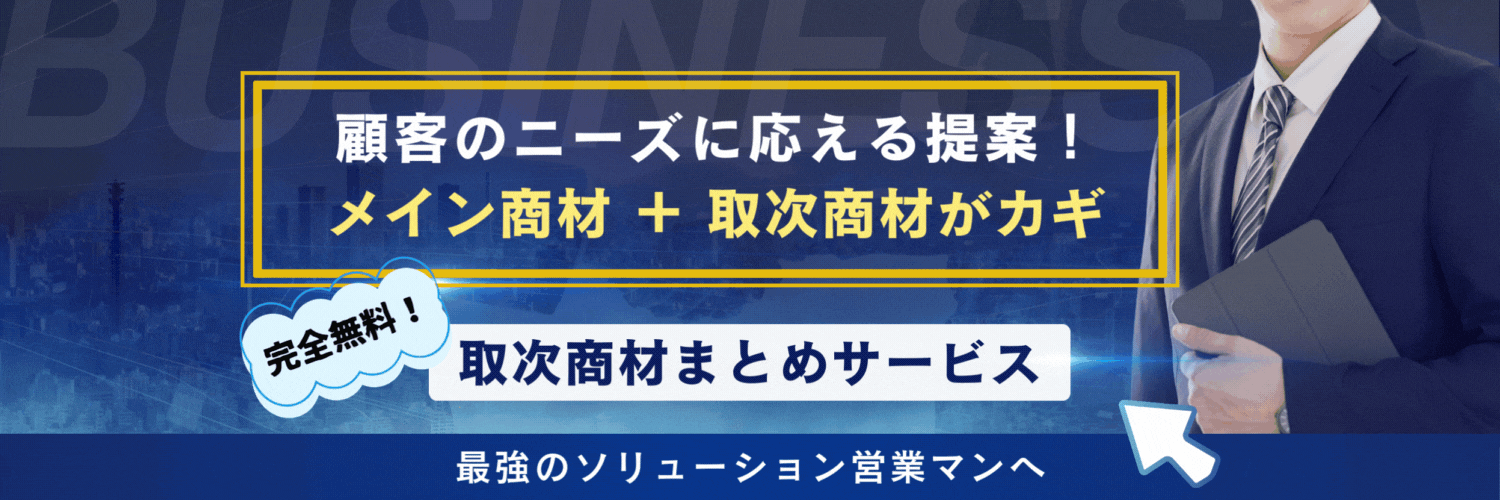はじめに
営業において「話す内容」ばかりに意識が向きがちですが、実はちょっとした言葉の使い方が大きな差を生みます。その一つが ネームコーリング(名前を呼ぶこと) です。
人は自分の名前を呼ばれると、自然と注意が向き、心が開きやすくなります。逆に、名前を一度も呼ばれないまま話が進むと、「誰にでも同じことを言っているのでは?」と感じ、信頼関係を築きにくくなります。
本記事では、営業で成果を上げるためのネームコーリングの活用法を、失敗例も交えながら紹介します。
ネームコーリングが営業で効く理由
「自分ごと化」される
人は名前を呼ばれると「これは自分のことだ」と感じ、話を真剣に聞きやすくなります。
例えば「この資料をご覧ください」よりも「田中さん、この資料をご覧ください」の方が、相手の意識はぐっと集中します。
また、顧客はテンプレで提案されているのでなく、自分のために話してくれている気持ちになります。
信頼感が高まる
名前を呼ばれると「覚えてくれている」「自分を大切にしてくれている」と感じます。特に初対面やまだ関係が浅い相手には、名前を使うことが距離を縮める第一歩になります。
特にアイスブレイクの会話で名前を呼ぶことで、一気に距離を縮めることができます。
会話のリズムが生まれる
名前を適度に挟むことで、会話が単調にならず、リズムが生まれます。聞き手が「自分に話している」と自然に感じられるのです。
やりがちな失敗例
名前を一度も呼ばない
初めて会ったときに名刺交換をしても、その後まったく名前を呼ばずに話し続ける新人は多いです。これでは相手は「覚えてくれていない」と思い、距離を感じます。
名前を間違えたらと不安になるのもわかりますが、積極的に名前を呼びましょう。
特に名刺交換をしたタイミングで名前を呼ぶと、自分自身にも記憶として残るのでおすすめです。
呼びすぎて不自然になる
「田中さんはどうですか?」「田中さんならこうですよね」と、やたらと名前を繰り返すと逆効果です。わざとらしく聞こえ、営業トーク感が強まってしまいます。
普段どんなときに名前を呼んで会話していますか?
その感覚を大事にして会話しましょう。
呼び方を間違える
名前を読み間違えたり、役職や敬称を省略してしまうと失礼にあたります。特に漢字の読みが難しい名字は要注意。事前にしっかり確認しておきましょう。
難しい漢字だった場合は、あえて「難しい漢字ですね。なんて読むんですか?」という会話からアイスブレイクに進むのもいいでしょう。
ネームコーリングを効果的に使うタイミング
話の切り替え時
「田中さん、ここからは今回のご提案についてご説明します」
名前を添えることで、会話の切り替えがスムーズになります。
質問するとき
「佐藤さんは、この点についてどうお考えですか?」
質問に名前を加えると、指名感が生まれ、答えやすくなります。
共感を示すとき
「鈴木さんのおっしゃる通りですね」
相手の発言を肯定しながら名前を呼ぶと、共感が強調され、信頼感が深まります。
初めて挨拶するとき
「高橋さんと仰るんですね!よろしくお願いします」
相手の名前を憶えて呼べるように、まず挨拶タイミングで口にしましょう。
実践のコツ
会話の中で自然に使う
大切なのは「自然さ」です。無理に名前を連呼せず、必要な場面でさりげなく使いましょう。
相手の好む呼び方を尊重する
「田中課長」「田中さん」「田中様」など、呼び方一つで印象は変わります。相手が普段呼ばれている形に合わせるのが安心です。
あえて「下の名前で呼んでもいいですか?」と聞いて、下の名前で呼ぶと仲良くなれる場合もあります。
複数人の場では公平に
会議や打ち合わせで複数人がいるときは、一人だけでなく全員の名前をバランスよく呼ぶように意識しましょう。
ケーススタディ:ネームコーリングで商談が変わる
ケース1:名前を呼ばなかった場合
新人営業Aさんは、商談中に一度も相手の名前を呼ばず、「こちらの商品は…」と説明を続けました。結果、相手の反応は薄く、「また連絡します」と言われて終わってしまいました。
ケース2:名前を適度に使った場合
一方、Bさんは「山本さん、この部分はいかがですか?」と適度に名前を使い、相手の意見を引き出しました。相手は自然に会話に参加し、商談が盛り上がり契約につながりました。
この差を生んだのが、わずかな「名前の使い方」なのです。
まとめ
ネームコーリングは、誰でもすぐに実践できる営業スキルです。
- 名前を呼ぶことで相手の意識を集中させられる
- 信頼感や安心感を与えられる
- 会話が自然にスムーズになる
ただし、「呼ばない」「呼びすぎ」「間違える」といった失敗には注意が必要です。
営業は商品やサービスを売る前に「人と人との信頼関係」を築くことが大切。その第一歩として、相手の名前を大切に扱いましょう。小さな工夫が、大きな成果につながります。