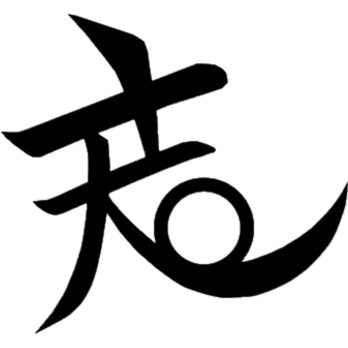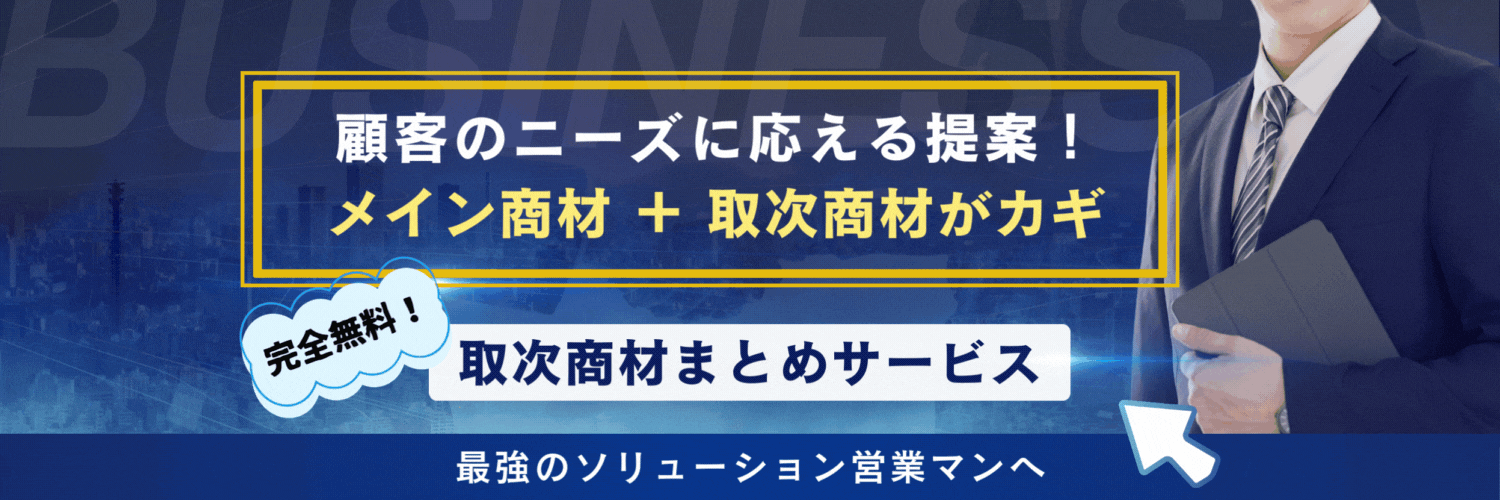営業が交流会を主催する時代に
「営業=売ること」と思われがちですが、現代における営業は「信頼関係の構築」に重きが置かれるようになっています。
その手段として注目されているのが、「交流会の主催」です。
交流会といえば参加するもの、という印象を持たれるかもしれませんが、今や営業マン自身が企画し、自らのネットワークを広げていくケースが増えています。
ですが、「交流会をやってみたいけど、どう設計すればいいのかわからない」「集客が不安」といった声も多く聞かれます。
本記事では、営業マンが交流会を成功に導くために欠かせない、設計という視点からのステップ別ノウハウをお伝えします。
なぜ「設計」が交流会の成否を分けるのか?
交流会が成果につながるか否かは、「その場の雰囲気」や「参加者の層」など、企画段階から決まっているといっても過言ではありません。
つまり、いくら当日がうまくいっても、設計に無理やズレがあると、
- 想定した顧客層が来ない
- 雰囲気がバラバラで話が広がらない
- 主催者としての印象が残らない
- 参加者が満足できず、マイナスな評判が立つ
といった、もったいない結果になってしまうのです。
逆に、きちんと設計された交流会は、「あの人の会なら参加したい」「知人にも紹介したい」と評判が広がり、営業成果につながる資産になっていきます。
ステップ①:交流会の目的を明確にする
まず最初にやるべきは、「なぜ交流会をやるのか?」という目的の明確化です。
これはすべての設計に関わる土台です。
たとえば以下のような目的があります
- 自分の商品やサービスに興味を持つ人と出会いたい
- 将来の紹介パートナーを見つけたい
- 既存顧客との関係を深める場をつくりたい
- 異業種とのつながりを広げたい
- 深い人間関係を構築できる人と出会いたい
目的によって、集める人・話す内容・規模感・時間帯すらも変わってきます。
「営業につなげたい」の一歩手前の目的を丁寧に言語化するのが、最初の設計ポイントです。
ステップ②:ターゲット(参加者像)を設定する
次に、「誰に来てほしいか?」を考えましょう。
これは、業種や職種だけでなく、
- どんな課題やニーズを持っている人か?
- どのくらいの人脈を持っているか?
- 自分のサービスとどんな接点があるか?
といった、属性や温度感も含めて具体化することが重要です。
例:「中小企業の経営者で、人材定着や組織作りに課題を感じている人」
→ 自身が人材育成のサービスを提供している営業マンなら、そこに刺さる
これにより、無駄な集客や場のズレを防ぐことができます。
また、参加してほしい人の年齢層や参加NGの職種なども検討しておきましょう。
逆に、この仕事をしている人だけ限定という方法もアリです。
ステップ③:テーマ・形式を決める
ターゲットが決まったら、次はテーマと会の形式です。
テーマの決め方
テーマは「集客力」と「参加者の安心感」に直結します。
漠然とした「異業種交流会」ではなく、ある程度の方向性を持たせるのがコツです。
例:
- 「30代〜40代の個人事業主が集まるリアル交流会」
- 「地元企業と士業をつなぐランチ会」
- 「営業初心者のための雑談練習交流会」
- 「協業仲間を探す多業種交流会」
テーマが明確だと、「自分向けだ」と感じた人が集まりやすくなります。
会の形式(スタイル)
次に会の形式を考えましょう。
昼に開催するのか、夜に開催するのか?
平日にするのか、土日に開催するのか?
参加してほしいターゲットが集まりやすい日時で設定しましょう。
会の形式例
- 時間:60〜90分がベスト。初回は短めに
- 人数:4〜6人(少人数の方が濃い関係に)
- 場所:カフェ、会議室、オンラインなど自由
- 内容:アイスブレイク → 自己紹介 → フリー交流
- 会費:自分が頼んだ分だけ
最初は無理にワークやプレゼンを入れず、自然な会話を大切にすると好感度が高まります。
会費はお店や、食事やドリンクをどうするかによって異なります。
これも、ターゲットのニーズに合わせて設定しましょう。
ステップ④:集客のポイント
交流会を設計しても、人が集まらなければ成立しません。
でも、最初から大人数を集めようとすると失敗の元です。
最初は信頼できる身近な人から声をかける
- すでにつながっている顧客・知人
- 「○○さんに会わせたい人がいる」と思ってくれる人
- 自分の想いに共感してくれる仲間
集客において大切なのは、「人」ではなく「つながり」です。
最初は紹介を頼るのもOK。人数が少なくても、信頼度の高い場をつくることが優先です。
また、あなたの周りに集客が得意な人がいる場合は、協力を仰ぐのもいいでしょう。
告知文の基本構成
- 交流会の目的(なぜやるのか)
- どんな人に来てほしいか
- 参加者が得られるメリット
- 日時・場所・参加費などの詳細
- 定員・申込方法・主催者のプロフィール
文章は短く・具体的に。画像や過去の雰囲気写真があると、安心感が増します。
ステップ⑤:当日のシナリオと準備
当日は、主催者として場を円滑に進行する役割も担います。
以下のようなシナリオがあるとスムーズです。
- 受付・名札配布
- 開会挨拶(目的を一言伝える)
- 自己紹介タイム(1人90秒〜2分)
- フリー交流(お題やテーマがあると話しやすい)
- クロージング(お礼+次回案内など)
また、事前にチェックすべき準備物
- 名札・ペン・プロフィールカード
- 飲み物や軽食(必要なら)
- 自分の名刺、案内資料
- 連絡グループ(LINE・Facebookなど)
交流会はつながりを演出する舞台でもあります。準備を丁寧に行うことで、参加者の満足度と印象は大きく変わります。
参加人数が多い場合は、主催メンバーを増やすことがおすすめです。
主催メンバーの仕事の振り分けも事前に準備しておきましょう。
まとめ:「設計=相手目線」の営業発想
営業マンが交流会を開くことは、単なる集まりではありません。
そこには「誰のために」「どんな価値を」「どう届けるか」という、まさに営業の本質があります。
だからこそ、
- 目的とターゲットを明確にし
- 自然に話せるテーマと形式を整え
- 少人数でも信頼できる人から始め
- 丁寧な準備で場をつくる
この一連の設計が、「信頼される営業」としての第一歩になるのです。
交流会は売る場ではなく、つながりをつくる場。
そこから生まれた関係性が、やがて顧客やパートナーへと育っていく
その未来を設計するのは、あなたの一歩です。