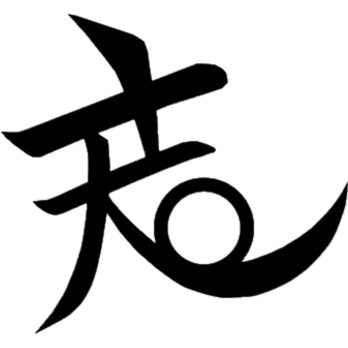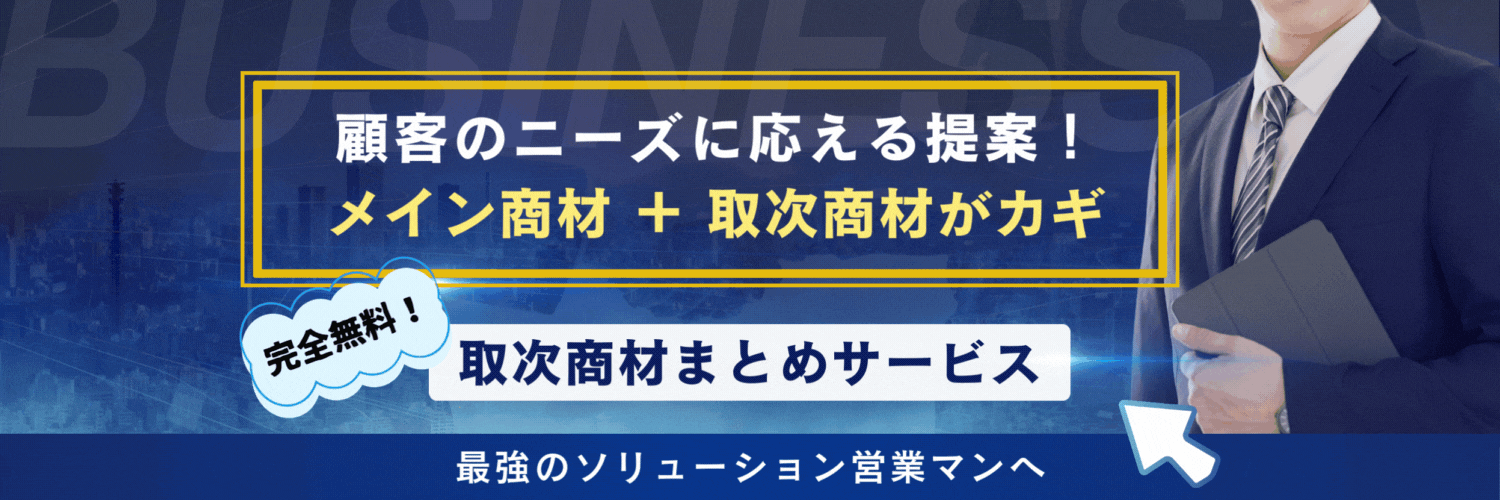― 顧客の意思決定を自然に導く選択の心理学
営業において「提案内容は悪くないはずなのに、なぜか選ばれない」そんな経験はないでしょうか?
実は、顧客が何かを「選ぶ」場面では、提案内容そのものだけでなく、「どのように提示されたか」が選択に大きく影響します。
人は、合理的に意思決定しているように見えて、実際には無意識に心理的な影響を受けて選んでいるのです。
その中でも、営業で知っておきたい心理テクニックが「デコイ効果(おとり効果)」。
この記事では、デコイ効果とは何か、その仕組みと活用方法、そして営業現場での実践例を交えながら解説していきます。
デコイ効果とは?――意思決定に影響を与える「第三の選択肢」
デコイ効果とは、人が選択肢を比較する際に、意図的に追加された「おとり」的な選択肢によって、他の選択肢の魅力が引き立つ現象のことです。
行動経済学でも広く知られており、マーケティングや営業戦略においても頻繁に活用されています。
事例:映画館のポップコーン
映画館でこんな価格設定を見たことがあるかもしれません。
- 小サイズ:300円
- 中サイズ:500円
- 大サイズ:550円
この場合、多くの人が「大サイズ」を選びます。なぜでしょうか?
中サイズと大サイズの価格差がたった50円。
しかも容量は大幅に違うとすれば、「中を買うくらいなら、大を選んだ方が得だ」と感じるわけです。
ここでの「中サイズ」は、実は「大サイズを選ばせるためのおとり(デコイ)」です。
大サイズを選んでもらうために、わざと損を感じさせる中サイズを販売しているのです。
なぜデコイ効果が起きるのか?
人は選択を迫られたとき、「絶対的な価値」ではなく「相対的な比較」で判断します。
つまり、AとBのどちらがいいかではなく、「AとBとCを見比べたとき、どれが最もお得に見えるか」という視点で選んでいるのです。
日本人は損をすることを極端に嫌うこともあり、一番お得な選択をしたい気持ちが強い人種です。
デコイ効果はこの「相対的な判断基準」に働きかけることで、顧客の意思決定を自然に導く力を持っています。
営業で使える!デコイ効果の活用パターン
デコイ効果は、価格設定やプラン設計、オプション提案など、営業において幅広く応用できます。ここでは、営業シーンで使える具体的な活用例を紹介します。
プラン比較提案での活用
たとえば、ソフトウェアの提案において以下のようなプランがあったとします。
- ライトプラン:月額5,000円(基本機能のみ)
- スタンダードプラン:月額8,000円(基本+便利機能)
- プレミアムプラン:月額8,500円(スタンダード+カスタマーサポート強化)
この場合、「スタンダード」と「プレミアム」の価格差はわずか500円。
「どうせならサポートも付くし、プレミアムにしよう」と思わせやすくなります。
このとき「スタンダードプラン」がデコイ(おとり)の役割を果たしているのです。
商品Aではなく、商品Bを選ばせたいとき
顧客に商品Bを選んでもらいたい場合、その商品よりも見劣りする「似たような価格・スペック」の商品Aを横に並べて見せます。
- カメラA:従来の基本モデル、価格10万円
- カメラB:上位モデル、価格11万円
このようにすると、「たった1万円の差でこれだけ性能差があるなら、Bの方が得だ」と感じる心理が働き、商品Bが選ばれやすくなるのです。
似たような商品で少し見劣りする商品を横に置くだけで、一番売りたい商品に顧客の気持ちを誘導させることができるのです。
店舗で営業している場合のレイアウトに意識して活用すると大変効果的です。
オプション提案の際の比較トリック
基本プランにオプションを追加する際、あえて「やや中途半端なオプション」を提示することで、フルセットのオプションの魅力を引き立てることができます。
- 基本プラン:10万円
- オプションA(限定的な機能追加):+3万円
- オプションB(すべての機能追加):+4万円
このとき、オプションAが中途半端に高く見えるため、結果としてBが選ばれやすくなるのです。
自社で金額設定や提案内容を設定する場合は、このように顧客にどこを選んでほしいか考え、それに合ったプランを作成する必要があります。
その際は、デコイ効果も意識して設定しましょう。
デコイ効果を使うときの注意点
便利なテクニックとはいえ、デコイ効果を誤って使うと、「操作された」と顧客に不信感を与えることもあります。
以下のポイントを押さえて、誠実に使うことが大切です。
あくまで顧客にとっての価値が前提
デコイ効果はあくまでも判断を助けるための「補助線」です。
最終的な価値が伴っていなければ、逆に「ごまかされた」と思われてしまいます。
「ごまかされた」と思われると、信頼関係に傷がつき逆効果となってしまします。
そのためにも「どのプランも誠実に価値がある」と胸を張って言えるラインナップ設計を心がけましょう。
不自然な選択肢は逆効果
「誰が見ても選ばれないような明らかなダミー」を提示すると、顧客はその意図に気づき、不信感を持ちます。
「本当に迷うけど、結果的にこっちを選びたくなる」レベルの絶妙な差を設計することが成功のカギです。
自分自身では絶妙だと思っていても、ずれていることは多々あります。
絶妙な設計になっているかは、第三者に意見を聞くことがおすすめです。
デコイ効果を自然に活かす営業とは
営業において、重要なのは「選ばせる」のではなく、「選びやすくしてあげる」ことです。
デコイ効果は、相手の心理に寄り添いながら、より納得感のある意思決定をサポートするためのツールです。
押し売りではなく、顧客に「自分で選んだ」と思ってもらえる流れを作れる営業は、結果的に高い満足度と信頼を得られます。
営業自身も、「売るため」ではなく、選びやすくサポートしている気持ちでデコイ効果を活用しましょう。
まとめ:選択の設計力が、営業力を高める
営業の提案とは、単に商品やサービスの内容を伝えるだけではありません。
顧客が「どれを選ぶか」を決めるとき、その選び方そのものを設計できる営業こそが、結果を出し続けられる営業です。
デコイ効果を理解し、誠実に、戦略的に活用することで、提案力は一段と高まり、成約率も自然と上がっていくはずです。
明日からの提案に、ぜひおとりの力を一つ加えてみませんか?